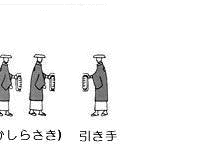
| 引き手(ひきて) | |
| 施主の依頼を受けて、家までの案内をする。 | |
| 頭先(かしらさき) | |
| 三ツ葉葵の紋付き羽織を着て、組を誘導する。 | |
| 頭(かしら) | |
| 「ひんどうろう」ともいう | |
| 幟(のぼり) | |
| 武将の旗指物をかたどったもので、組の標識としている。 | |
| 双盤(そうばん) | |
| 2個の鉦(かね)を並べて、布を細く切って束ねた撞木で打つと、それぞれの音が調和して独自の音を発する。 | |
| 笛 | |
| 6穴の横笛で、笛の音に合わせて行進、施主の家へ入場する。 | |
| 摺鉦(すりしょう) | |
| 小さな鉦(かね)のことで、主として笛と共に行進の時に打ち鳴らす。 | |
| 太鼓 | |
| 4個1組で用い、遠州大念仏では太鼓を打つことを「きる」という。8拍子と16拍子がある。 | |
| 供回り(ともまわり) | |
| 行列の形をそろえて、回向の歌い手となる。 | |
| 押し | |
| 道中行進の秩序を整える。 | |
| 犀ヶ崖資料館 パンフレットより引用 | |